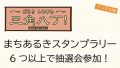※本ツアーは開催前です。

南海沿線ツアー第7弾【健脚コース 11.9㎞】
南海電鉄の高野線 滝谷駅 から 河内長野駅 をぶらり巡るツアーを、富田林市・河内長野市・南海電鉄で共同企画いたしました。
すべてのスタンプを獲得されアンケートを記入された方に「がんばった賞」として(健脚・家族向け各コース通算で)先着100名様に南海電鉄オリジナルグッズをプレゼント。
さらに、大阪府民の健康サポートアプリ「アスマイル」のイベント参加ポイント(500ポイント)も獲得できます。
「がんばった賞」及び「アスマイルイベント参加ポイント」は、【河内長野市観光案内所】で受け取れます。(お一人様一回限り)
ゆっくり歩かれるも良し、自転車で散走されるのも良し、是非南海沿線の観光をご堪能ください。
南海沿線ツアー第7弾に関する問い合わせ先
南海コールセンター
050-3090-2608 (8:00~21:00)
ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「32337」で検索してください。
アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。
【滝谷駅】
大阪府富田林市

高野鉄道の狭山駅~長野駅間が開通した明治31年(1898)3月、東へ約3キロの位置にある「瀧谷不動明王寺」への参詣駅として開業しました。
明治35年(1902)3月に河南鉄道の滝谷不動駅(現・近鉄長野線)が開業するまで最寄り駅として利用されました。眼病平癒で有名な瀧谷不動は、弘仁12年(821)弘法大師開創と伝えられ、毎月28日の縁日には大勢の参詣客でにぎわいます。
駅から東へ徒歩約20分の「錦織公園」は、野山や池などをそのまま生かした自然公園で、野鳥や草花の観察に適しています。当社線で富田林市内にある唯一の駅です。
南海電鉄 > 電車・駅のご案内 > 駅・時刻表 > 滝谷
https://www.nankai.co.jp/traffic/station/takidani.html
(2025年3月3日取得)
【千代田神社】
大阪府河内長野市

【歩行情報】滝谷駅から約2500ⅿ
【参考】千代田駅から1300ⅿ
【千代田神社】
東高野街道沿いに建っている千代田神社は、菅原道真公を祀っており、ご神体は平安時代に作られたといわれる桧材の菅原道真座像、それともう一体当時周辺に住んでいた住民の祖先の神と思われる像があります。
昔から国家に認められる格式ある神社で、皇室の記念碑や君が代で知られる「さざれ石」が置かれています。
河内長野でさざれ石を見られるのは、千代田神社だけのようです。
毎年7月に開催される「千代田天神祭」では、限定のお守りや御朱印が授与でき、屋台や手作り市、フリーマーケットに音楽フェスも行われ、大いに盛り上がります。秋祭りでは、だんじりが宮入りする場所でもあります。
河内長野観光ナビ > モデルコース > 七社めぐりコース ❽
https://kankou-kawachinagano.jp/course/1449
(2025年3月14日取得)
【さざれ石】千代田神社の案内看板より一部引用
「さざれ石」とは長い年月をかけて大小の石が集結し大きな岩と成ったものである。
【目白不動 願昭寺】
大阪府富田林市

【歩行情報】千代田神社から約1500ⅿ
*願昭寺の手前約650mは住宅街を抜けて12%の上り勾配で急な坂道となっています。
【目白不動 願昭寺】
信者手作りの寺として知られる寺で、本尊は樹齢800年の老木を丹念に彫り上げられた楠木の一刀彫りです。
また、ここは梅の名所としても知られています。
魅力発信・観光ポータルサイト > 文化財 > 目白不動願昭寺
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kirameki/14586.html
(2025年3月14日取得)
【腰神神社】
大阪府富田林市

【歩行情報】目白不動 願昭寺から約1100ⅿ
【腰神神社】
腰神神社は金胎寺山の山麓の巨岩をご神体とする神社で、由緒書によると、7世紀の半ばごろ、紀伊国の豪族箕島宿禰が嬉に移り住み、河内国に文武を広めた功績をたたえられて腰神神社に祭られたのがはじまりと伝えられています。
その後、南北朝時代に、楠木正成が鎌倉討伐に向かう道中、腰を痛めて歩けなくなった正成の馬を、腰神神社の藤の木につないで休みをとらせたところすっかり良くなり、腰神神社で勝利を祈願し出陣したという言い伝えがあり、いつのころからか腰の神さまとして知られるようになりました。
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 子育て・教育 > 文化財 > 文化財課 > 嬉の腰神さん
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/bunkazai/2567.html
(2025年3月14日取得)
【金刀比羅神社】
大阪府河内長野市

【歩行情報】腰神神社から約700ⅿ
【金刀比羅神社】
金刀比羅神社(ことひらじんじゃ)は、香川県の金刀比羅宮(ことひらぐう)を総本宮としています。
【奥河内さくら公園】(遊具)
大阪府河内長野市

【歩行情報】金刀比羅神社から約1700ⅿ
*奥河内さくら公園の手前約250mは13%の上り勾配の急な階段・坂道となっています。
【奥河内さくら公園】(遊具)
長野公園の顔となる回廊風休憩所は現在建て替え中です。
【河合寺 バス停】
大阪府河内長野市

【歩行情報】奥河内さくら公園から約450ⅿ
【河合寺 バス停】
近くに、河合寺「子育て慈母観音」や「由緒書き」があります。
また、「長野公園(河合地区)」へは、こちらのバス停が便利です。
【多聞丸(楠木正成) 大江時親に学ぶ像】
大阪府河内長野市

【歩行情報】河合寺(バス停)から約1800ⅿ
*スタートして約600mは7%の上り勾配の坂道となっています。
*三日市町駅を目指して歩行してください。
(河合寺交差点(信号機)右折・住宅地を抜ける・大師町バス停を右折直進・幼稚園に沿って左側坂道をくだる・・・)
【多聞丸(楠木正成) 大江時親に学ぶ像】
本地域には、楠木正成が幼少期に、観心寺(本市川上地区)の学問所から、兵法を学ぶた
めに大江時親邸(本市加賀田地区)まで通ったとされる道があり、地域の住民は、この道を
「楠公通学路(橋)」と呼ぶようになったと伝わっています。それにちなんで、「楠公通学路(橋)」の近くに、「多聞丸」が学んだ姿の石像を建立することとなりました。
河内長野市 報道提供資料(PDF)2018年3月6日
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/uploaded/attachment/4730.pdf
(2025年3月13日取得)
【旧三日市交番】高野街道
大阪府河内長野市

【歩行情報】多聞丸像から約450ⅿ
*西高野街道の一部です。
*旧三日市交番
開館日:土・日・祝日
開館時間:10:00~16:00
*都合により閉館していることもあります。
【河内長野市指定文化財旧三日市交番】
旧三日市交番は、昭和27年に建築され、平成19年に三日市交番が三日市町駅前へ移転するまで、地域の治安を守ってきました。
木造駐在所の形態を今日に伝える貴重な遺産であり、かつての宿場町の雰囲気を残す周囲の景観によく馴染んでいることから、平成22年10月7日に河内長野市の指定文化財となりました。
その後、平成23年6月からこの建物の保存修理を行い、当時の姿を再現しました。
修理の完了した平成24年8月、旧三日市交番は歴史・文化の情報発信の拠点としてオープン。
施設の運営は、三日市小学校区連合町会と市が協働で行い、高野街道三日市宿として栄えた地域の歴史と文化について情報を発信しています。
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 文化課 > 旧三日市交番について
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/57/4401.html
(2025年3月13日取得)
【烏帽子形八幡神社】
大阪府河内長野市

【歩行情報】旧三日市交番から約700ⅿ
*西高野街道の一部です。
【重文烏帽子形八幡神社本殿】
烏帽子形山の東麓に位置します。発見された棟札(むなふだ)によると、文明12年(1480)に石川八郎が建立したことがわかります。また江戸時代初め、この地の領主で最後の烏帽子形城主であったと言われている甲斐庄喜右衛門正房の子、旗本甲斐庄喜右衛門正保が、元和3年(1617)に四天王寺の普請奉行を勤め、その時の余材を使用して元和8年に神社の修繕を行ったと記録されています。
本殿は桁行3間、梁行2間の入母屋造、檜皮葺きの建物です。正面三方に縁をめぐらして、正面中央に擬宝珠をつけた5段の階段がつけられています。
また神社には徳寿院蒿福寺という天台宗の神宮寺がありました。この寺のものである鐘が奈良県五條市西吉野町賀名生の堀家に伝えられています。その銘文に河内蒿福寺と康元元年(1256)の年号が見られます。
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 文化課 > 重文烏帽子形八幡神社本殿
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/site/history/5591.html
(2025年3月13日取得)
【長野神社】
大阪府河内長野市

【歩行情報】烏帽子形八幡神社から約950ⅿ
*西高野街道の一部です。
【重文長野神社本殿】
長野神社の本殿は、一間社流造りで、正面に千鳥破風と軒唐破風がつき、屋根は檜皮葺きです。この建築年代は、天文18年(1549)の棟札のある観心寺の訶梨帝母天堂や天文12年の棟札のあった堺市の多比速比売神社本殿とも似ていますので、これらと同時代と推定されています。
長野神社は、明治初年の神社合祀でつけられた名称です。江戸時代には「木屋堂宮」あるいは「牛頭天王宮」と呼ばれていました。この「木屋堂」は正和2年(1313)の後宇多院御幸記に木屋堂御所の記載が初見です。その後も元弘3年(1333)の粉河寺文書や応永6年(1399)の日野観音寺大般若経奥書に「木屋堂」の記事が見られます。
大阪府河内長野市役所 > 各課のページ > 文化課 > 重文長野神社本殿
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/site/history/5590.html
(2025年3月13日取得)