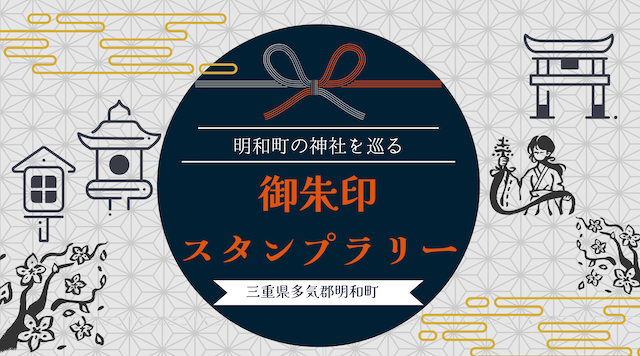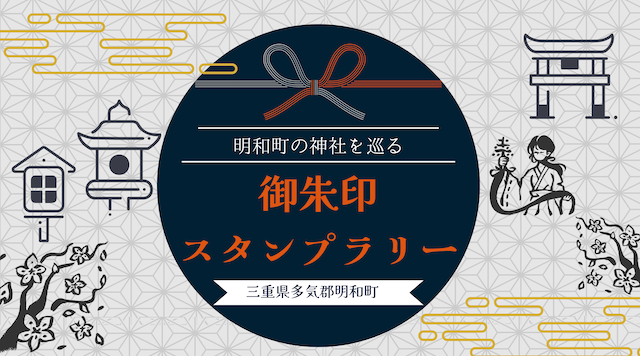
【三重県明和町の神社を巡るスタンプラリー(4月)】
明和町にある、宇爾櫻神社、竹神社、麻續神社、畠田神社、竹大與杼神社を巡るスタンプラリーです。
スタンプラリーの参加者は、普段いただけない神社の御朱印(書き置き)を受領することができます。
各神社の御朱印は、竹神社にて代わりに頒布いたします。スタンプラリーの竹神社の社務所開所時にお越しください。
【詳細事項】
※期間中であれば1日でまわって頂かなくても大丈夫です。
※スタンプラリーを達成後、竹神社の社務所開所時に、竹神社の社務所にお越しください。参拝いただいた神社の御朱印(書き置き)をお渡しします。
※スタンプラリーは無料ですが、御朱印の授与には初穂料が必要です。
※御朱印は書き置きとなっております。ご自身で御朱印帳にお貼りください。
※各御朱印の初穂料は、各神社にお納めいたします。
【竹神社社務所開所日】
■土日:10時〜15時
■満月の日:10時〜19時
■令和7年の満月参り
3月14日金曜日 4月13日日曜日
5月13日火曜日 6月11日水曜日
7月11日金曜日 8月9日土曜日
9月8日月曜日 10月7日火曜日
11月5日水曜日 12月5日金曜日
■その他
竹神社のインスタグラムのアカウントをご覧ください。
https://www.instagram.com/_takejinja/
【お問い合わせ】
運営:一般社団法人明和観光商社
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮3039-2
TEL/FAX:0596-67-6850 E mail:dmo@hana-meiwa.jp
ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「16516」で検索してください。
アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。
畠田神社 – はたけだじんじゃ –
三重県多気郡

【由緒】
当社の創始は明らかではありませんが、『延喜式神名帳』に「畠田神社三座」と記載されていることから、延喜年間(901~923年)には存在していたと推測されます。また『倭姫命世記』に、命(ミコト)が佐々牟江巡行の折、真名鶴が飛来して稲穂を咥えるのを見て「八握穂社ヲ祀ル」とあり、のちに根倉神社と改称し合祀されております。この真名鶴伝説では、当地が古くから米の産地であり、神宮の神嘗祭の発祥地であると伝えられております。
<行事>
6月には茅の輪神事が行われます。9月の収穫時期には、当社拝殿に篤志農家から新穀の稲束(カケチカラ)が奉納されます。
また9月25日には、カケチカラ発祥地(多気郡明和町根倉笹笛地区)にて新穀を奉納し、奉告祭が斎行されます。
12月には、注連縄奉納、かがり火奉納、年越し甘酒授与が行われます。
平成22年には、拝殿を新しく造営いたしました。今年も周辺の田んぼは綺麗に刈り取られて、美味しいお米が収穫されました。春には美しくなった畠田神社へお参り下さい。駐車場の桜も綺麗です。
【御祭神】
火之迦具土命、埴山比賣命、豊宇氣比賣命、饒速日命、天忍穂耳命、天津彦根命、熊野久須毘命、市杵島姫命、菅原道眞、大山祇命、蛭子命、品陀和氣命、建速須佐之男命、稚産霊命、宇麻志摩治命、天穂日命、活津彦根命、多紀理姫命、大日霊命、伊豆乃賣命、入船姫命、宇迦魂命、彌津波能女命、土之御祖命、戦没者英霊
竹大與杼神社 – たけおおよどじんじゃ –
三重県多気郡

【由緒】
当社の創始につきましては、「倭姫命世紀」に、皇女倭姫命が天照大神の御神霊を奉載して大淀の浦を航行された際、風浪がなく海水が「大与度に与度美」て御船の航路が安全であったために、命が大いに悦ばれ、大与度社を定められたとあり、垂仁天皇の御世に遡ると伝えられております。延喜式内社でございます。
明治39年、神饌幣帛料供進社に指定され、翌年には地区内の25社を当社に合祀し、竹大与杼神社と単称するようになりました。昭和26年には、豊歳稲荷神社を、また戦没者英霊を奉載する大霊神社を境内社としてお祀りし、現代に至ります。
江戸時代より、疫病退散、五穀豊穣、町内繁栄を祈念して、氏子の奉仕の下、山車が町内を巡行し、夜には花火大会が奉行されます。室町時代には、1月6日に二天八王子御頭神事が斎行された記録が、県文化財として残っております。
【御祭神】
建速須佐之男命 他20座
麻續神社 – おおみじんじゃ –
三重県多気郡

【由緒】
創始は不詳でございますが、上代まで遡るものと思われます。明治45年に豊城入彦命を祀る式内社の中麻續神社に、村内の佐賀茂神社、田中神社、粟須美神社、美里神社、宇気比神社須賀神社の六社が合祀され、その際に麻續神社と単称いたしました。昭和43年11月には坂本神社が分祀し、現在に至っております。
当神社は、国史跡『斎宮跡』の北に広がる田園地帯に鎮座しております。近くを歴代斎王の禊の場、祓川が静かに流れており、斎宮歴史博物館やいつきのみや歴史体験館等もほど近く、毎年6月の斎王まつりには内外から多くの人が訪れております。
宇爾櫻神社 – うにさくらじんじゃ –
三重県多気郡

【由緒】
当初の創始については明らかではありませんが、延喜神名式並びに延喜斎宮式にその名が見えます。平安時代には斎宮の祈念祭や新嘗祭に預かり、席別祭料として絹、木綿、麻、庸布、盾、鰒等が供進されておりました。江戸時代には有爾中村の北部に鎮座し、櫻宮あるいは櫻社と呼ばれておりました。
明治2年3月26日、勅使従三位橋本實梁が参加して弊帛及び金二千疋を奉納いたしました。同6年8月15日には現在の合戦田の地へ移転し、そしてこの地に祀られていた天王社を当社の相殿に奉祀し、櫻神社と改称いたしました。
同15年7月28日には、有爾中村蓑村に移された度会郡世古村の八柱神社分霊を、9月26日に合祀して村社に列しました。同41年6月30日、上野の仲神社など五社を合祀し、更に44年5月22日には宇爾櫻神社と改めました。
昔からの住宅地域からは少し離れている小高い森林に囲まれ、緩やかな長い階段を上りながら左に竹林が続き、時期には紫陽花の花が心を和ませてくれます。七月の例祭は天王祭りとも称し、「羯鼓踊り(かっこおどり)」が奉納されます。この時だけは地元、他地区だけでなく県外の方々の参詣者やカメラマンで賑わいます。
【御祭神】
木花之佐久耶比賣命・建速須佐之男命・天之忍穂耳命・天之菩卑能命・天津日子根命・活津日子根命・熊野久須毘命・多紀理毘賣命・市寸嶋比賣命・多岐都比賣命・神八井耳命・不詳一座
竹神社 – たけじんじゃ –
三重県多気郡

【由緒】
第11代垂仁天皇の御代、竹連(たけのむらじ、竹氏という豪族)の祖宇加之日子の子の吉日古が、天照大神を奉じて伊勢御巡行中の倭姫命のお供をしてこの地に留まり、多気郡一円を領して斎宮に住みます。この竹氏の子孫が祖神宇加之日子・吉日古を祀ったのが当社でございます。当社はもと旧参宮街道の竹川から北へ約300m進んだ松林の中(博物館南側駐車場前の奥の林)にありましたが、明治44年旧斎宮村内の23社を合祀し、現在の地に移されました。当社は旧斎宮全村はおろか多気郡全体の総祖神であるといえ、延喜式神名帳その他古書にその名が載っております。
斎宮には第38代天智天皇の頃より660年間、天皇に代わって伊勢神宮に仕えた斎王がおられましたが、斎王が住んでいた内院が当社の境内地に所在したのではないかといわれております。また「斎宮の世だめし」といわれ、馬が背負った稲束の色によって豊凶を占う「絵馬」が神宝として本殿に保管されております。
【御祭神】
長白羽神、 天照大御神、建速須佐之男命、八柱神、応神天皇、地主神、火産霊神、宇迦御霊神、大己貴命、天棚機姫命、八千々姫命、瀬織津姫神
【社務所開所時間】
土曜日・日曜日:10時〜15時
満月の日:10時〜19時
【その他情報】
駐車場:有
トイレ:有